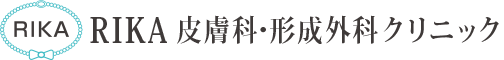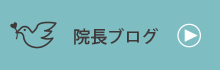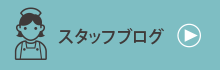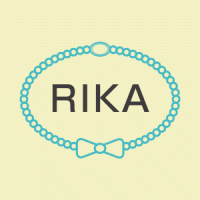手湿疹について
常に頻回の手洗いをし、手を酷使している私ですから当然手荒れはあるのですが、日常の診療では、赤ちゃんや小さいお子さんから大人まで、体やお顔の皮膚を触らせてもらうことが多いため、ガサガサしていたりしてはいけないと思って気をつけています。
この季節、手湿疹で受診される方も多いため、まずは基本的なことを少しだけ説明しますね。
手湿疹と一言でいっても、発症機序からは、刺激性接触皮膚炎、遅延型アレルギー性接触皮膚炎、タンパク質抗原対する接触皮膚炎、アトピー型手湿疹、そしてこれらが組み合わさっているものと、様々です。皮疹(症状)からいっても、角化型、進行性手掌角皮症、貨幣状湿疹、水泡型、乾燥・亀裂型などに分類されます。
原因や症状にかかわらず共通する手の平の皮膚の特徴から説明してみます。
① いろいろな物をさわるため、刺激をうけやすいこと
② 刺激から守るため、角質が厚いこと
③ 汗腺(汗の分泌線)が発達していること
④ 毛包がなく、皮脂の分泌がないこと
厚い角質を壊してうような外からの刺激が加われば、刺激性の接触皮膚炎をおこします。
また、 汗がたりなければ 皮膚の乾燥をもたらし、汗の排泄障害がおこれば汗疱や異汗性湿疹(汗の線と関係がある湿疹)がおこります。時には、汗に含まれ物質、特に食物のなかの金属で湿疹をおこすこともあります。
そして、手湿疹の難しさは、トラブルがあるからといって安静にできず、使い続けなければいけないから、バリア機能の壊れた皮膚にさらなる刺激が加わり、悪循環に陥りやすいのです。
特にバリア機能の低下は、皮脂欠乏性湿疹のブログにもでてきましたが、刺激性の接触皮膚炎のみでなくアレルギー性の接触皮膚炎もひきおこしやすいといわれています。
では、手の平の厚い角質が壊れるのは、どうしてでしょうか。
角質の水分を保持するものとしては
①皮脂②角質細胞間脂質(セラミド) ③ 親水性の天然保湿因子
の3つがあります。
先ほど説明した手の平の皮膚の特徴を思いだすと、毛包がないため皮脂が分泌されず、セラミドなどの角質細胞間脂質は普段は水には溶けにくいのですが、長時間水やお湯を使うと減少します。さらに親水性の天然保湿因子は頻回の手洗いなどによって溶出して減少します。
このようにバリア機能の低下が起こっています。こういうこともふまえて、治療について少し説明します。
基本的な治療では、
①原因物質、刺激因子からの回避
②保湿剤
③手袋を用いること
④炎症を伴う症例にはステロイド外用薬などの外用
⑤抗ヒスタミン薬内服
などです。症状が改善しない場合には、時には、パッチテストなどの検査や発症時期、部位、家事、職業歴、趣味、発汗との関係などの詳細な悪化因子の検討も必要となります。
軽症のものは、保湿剤のみで軽快することもあり、病院で処方される保湿剤としては、 白色ワセリン、尿素軟膏(ケラチナミン 軟膏など)、ヘパリン類似物質(ヒルドイドソフト軟膏)などがあります。
市販のものではセラミド(角質細胞間脂質)が含まれているものも販売されています。
その他、撥水作用優れたバリアクリームも販売されていて、水仕事の多い主婦、医療従事者、飲食業者では皮膚の保護効果を期待できます。
写真は、私の愛用のハンドクリームと保湿剤です。頻回にハンドクリームを外用するため、いろいろ揃えています。保湿剤では尿素軟膏に加え、最近ヘパリン類似物質のローションで泡状のものがでたので使ってみています。